理系数学の良問プラチカ 特徴
『理系数学の良問プラチカ』といば、大学への数学1対1の対応とともに難関大受験数学の登竜門的な参考書の一つですね。じゃあ実際自分が使ったかというと、使っていません。というか挫折しました(笑)だから落ちたんじゃ・・・
ということで、今回は自分が使った感想を記録していきます。使用していて何か違うなあと思っている人に刺さってくれたらいいなあと思って書いています。
特徴としては
- 演習力強化用参考書
- 誘導や条件設定の工夫、発想力を必要とする問題が多い
- 解説が丁寧で複数の解法に触れている
が挙げられると思います。これら細かく説明していきますね。
演習力強化用参考書ということ
よく比較される参考書に青チャートやFocus Gold、1対1演習がありますが、自分はこれらと比較してもしょうがないと思います。なぜなら、上記参考書が、例題と類題から知識を獲得していく問題集なのに対して、プラチカは数値を変えた類題がなく、その1問だけで知識を獲得していくからです。
イメージとしては、
100円均一なんかで、「これどこかで使いそうだな」と思って、買ったけど、実際出番がなくて、引き出しで眠っている。そんな解法の引き出しを獲得していく参考書になります。
実際自分が、東大や京大などを受験しないからその領域にいないだけかもですが・・・あくまでも演習力強化用参考書として、ナンプレを解くような気持ちで解いたら挫折しないと思います。そういう意味でもこの学習の記録をブログで残すのはいいことかも。
誘導や条件設定の工夫、発想力を必要とする問題が多い
よく参考書のレビューでは、「入試でよく問われるテーマを網羅」なんて書いてあるのですが、確かに、2次関数では、「区間が定まっているとき、定まっていないときの最大最小値」の問題があったり、数と式では、「相加相乗平均」を使う問題などがあります。しかし、そのテーマを使用してるだけで、応用が効くかというと、数値を変えた類題があるわけではないので、よくわかりません。
また、それよりも与えられた条件を変形して解きやすい形にもっていく
そういう問題が多い印象です。受験で差がつくテーマが入っていますが、それいつ使うねんがよくありますので、あくまでもナンプレの気持ちで解くといいと思います。
解説が丁寧で複数の解法に触れている
本書のはじめにの部分でも「解答に奇抜な考え方をするものをあえて採用していない」のように触れられていますが、まさにその通りです。問題冊子と解説冊子の厚さも全然違いますからね。また、解説の行間を自分なりに埋めることでさらに理解が深まると思います。そういう意味では、記録を残していくことは重要かも
理系数学の良問プラチカ 使い方
問題に取り組めそうであれば、解いた後に答え合わせで構いませんが、割と何をどうしたらいいかわからない問題が多いです。そこで、自分が行なっている方法を紹介します。
- 自力で考える(5分程度)
- 解説の解法のポイントを見て考える(5分程度)
- 解説を読み、ノートに書いてみる
- 問題の感想や学んだことを書いておく
とりあえず与えられた条件をこねくり回してみましょう。その結果行き詰まると思いますが、その思考過程もノートに書くことをしておくと、あとでノートを見返したときに役に立ちます。最後に、問題の感想や学んだことを記入しておきます。ノートでもいいし、問題の横に書いてもいいです。そうすると問題をもう一度見たときの記憶の残り方が全然違います。

理系数学の良問プラチカ 注意点
以上に私が行なっているプラチカの学習法を載せましたが、以下の点にも気をつけてください。さもないとモチベーションがめっちゃ下がります。
- パズルやクイズを解くような気持ちで取り組む
→問題が解けないと基礎力が足りないと勘違いする人がいますが、そうではないと思います。誘導や発想力を学ぶ問題が多いので、単元に関する知識があっても歯が立たない場合が多いです。楽に行きましょう。 - 全問できなくても気にしない
→志望校によって、解けた方がいい問題は変わってきます。問題に取り組んで、解説を見てもわからなければ、そこで足踏みするのではなく、いつかわかるだろうと思ってスルーしてもいいと思います。 - 問題を解いた回数を気にしない
→問題を解いた回数より、一通り問題集をやりきり、どの程度定着したかを考えた方がいいです。回数をこなしても定着しなければ、自分の数学の引き出しは一向に増えません。
まとめ
以上のようにこの参考書は、あくまでも演習力の強化を目的にして、いつ使うかわからない引き出しを1つでも多く増やすために使用するのがいいと思います。単元の知識を獲得するためだったら青チャートや1対1対応をはじめにやった方がいいですね。プラチカで、楽しみながら発想力を育てていきましょう。問題の条件設定をこねくり回すのが苦手なので、この参考書で練習したいと思います。
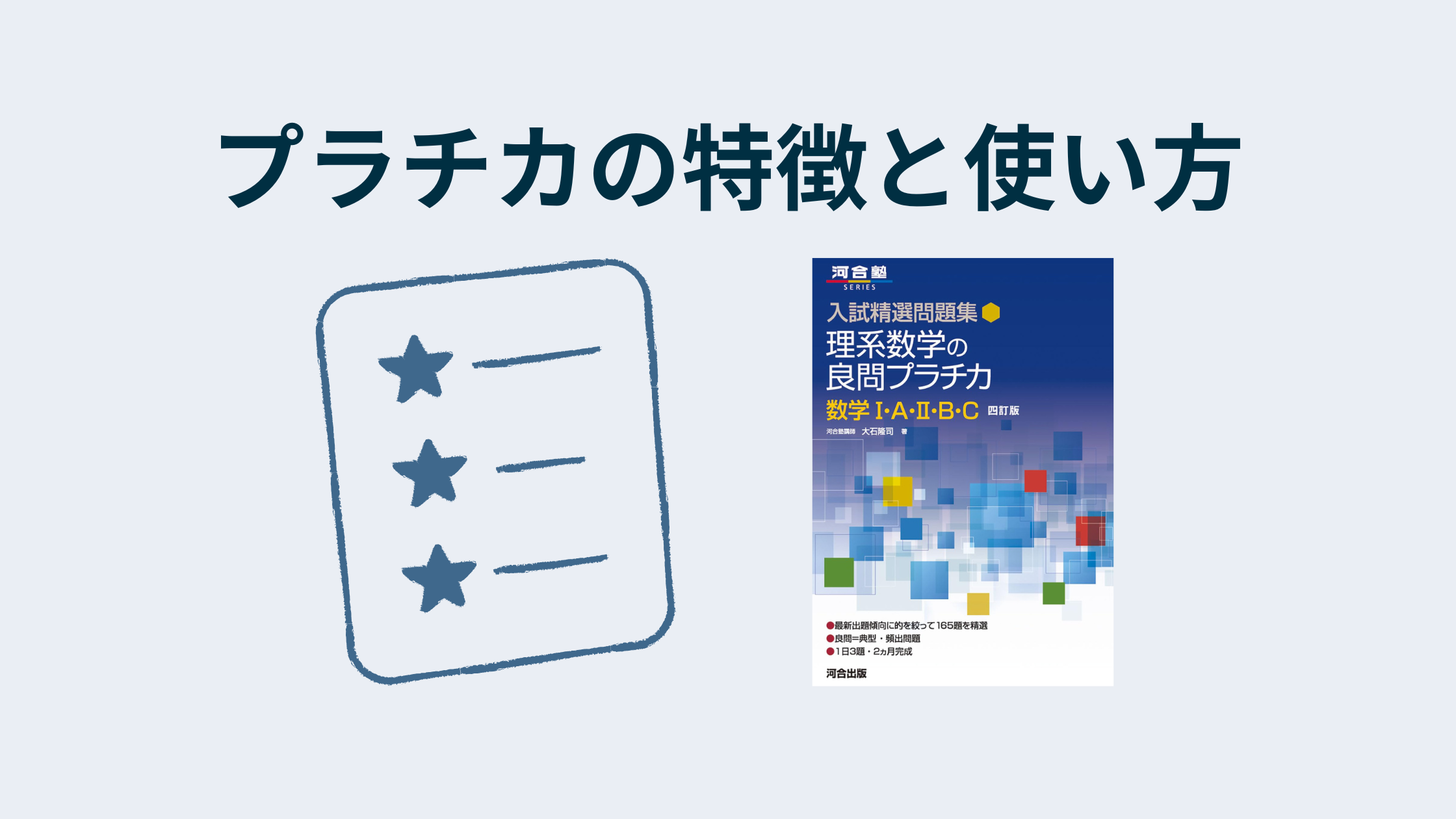
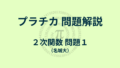
コメント