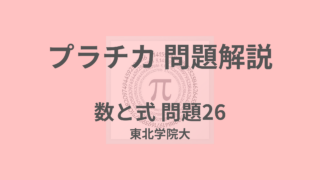 問題解説
問題解説 理系数学の良問プラチカ 問題解説26 (東北学院大)
問題円に内接する四角形ABCDにおいて, AB=2, BC=3, CD=4, DA=5 であるとき、次の問に答えよ (1) ∠CDA= \(\theta\) とするとき, cos\(\theta\) と sin\(\theta\) の値をそ...
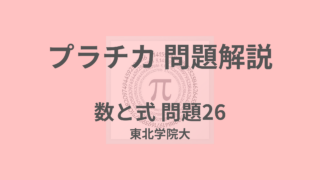 問題解説
問題解説 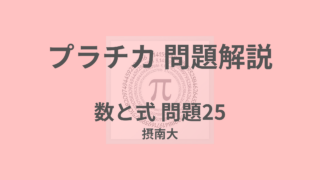 問題解説
問題解説 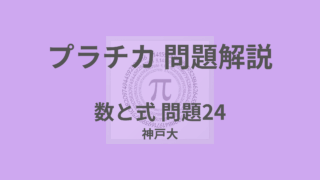 プラチカ
プラチカ 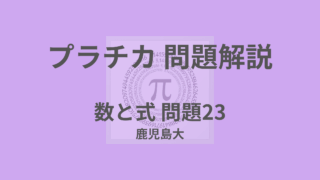 プラチカ
プラチカ 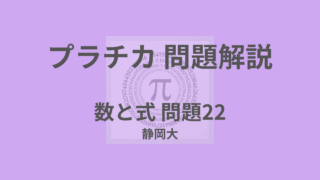 問題解説
問題解説 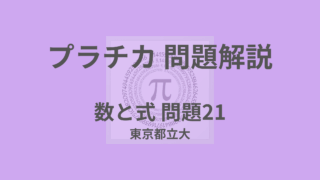 プラチカ
プラチカ 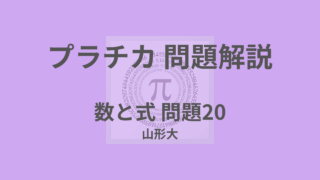 プラチカ
プラチカ 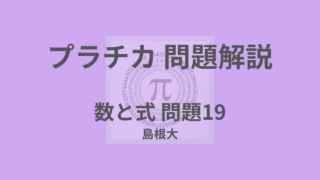 プラチカ
プラチカ 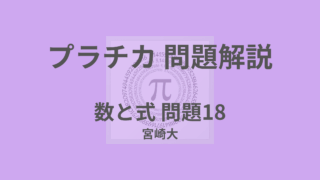 プラチカ
プラチカ 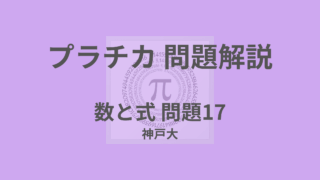 プラチカ
プラチカ