早速ですが、数学検定準1級合格を目指してみます。というのも、数学検定準1級は高校数学の集大成、久しぶりに高校数学を学び始めた自分の目標としてはちょうど良いかなと思っています。2024年度に数学検定2級を受けてみて合格したのですが、それと同じように学習して太刀打ちできるか、今回は、様々調べてみました。
数学検定準1級の難易度
数学検定準1級は数学検定の中でも難しい部類です。いかに理由を挙げていきます。
- 高校数学の全範囲が出題されるため、学習範囲が広い
→数学III(微分積分・複素数平面)や数学C(行列・ベクトル) など、大学入試共通試験より上位のレベルの内容も含まれます。 - 合格率は全体の20%〜30%
→1次試験の70%、2次試験の60%程度が解ける必要があります。
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 合格率 | 20.9% | 25.8% | 20.2% |
- より高い記述力が求められる
→大学入試でいえば 難関大の標準~やや難レベルの問題が解けるだけでなく、途中過程を論理的に説明する力が必要です。
数学検定準1級の出題範囲
- 高校数学の全範囲(数I・A・II・B・III・C) が対象
- 1次試験7問(マークシート)+2次試験5題より2題選択(記述)
→基礎力を幅広く問う1次試験が60分、応用力を問われる2次試験が120分の試験時間です。
数学検定準1級合格に必要な勉強時間
合格に必要な勉強時間は、学習者が高校数学をどのように学んでいたかにによります。自分は、一通り学びましたが、数学ⅢCはずっと学習していないので、②のタイプです。
- 1日2時間 × 週5日 → 約半年で300時間
- 1日1時間 × 週5日 → 約1年で250時間
ですので、約半年で合格を目指していこうと思います。
| 学習者のタイプ | 学習時間の目安 |
| ①一通り勉強していた人 | 100~150時間 |
| ②一通り学んだが、ブランクがある人 | 300~500時間 |
| ③深く学ばなかった人(文系出身者) | 600~800時間 |
まとめ
高校数学の集大成というだけあって、簡単には合格させてくれなさそうです。1日2時間ほど約半年学び続けられるか・・・このブログ等を通してモチベーションを保ちつつ頑張りたいです。
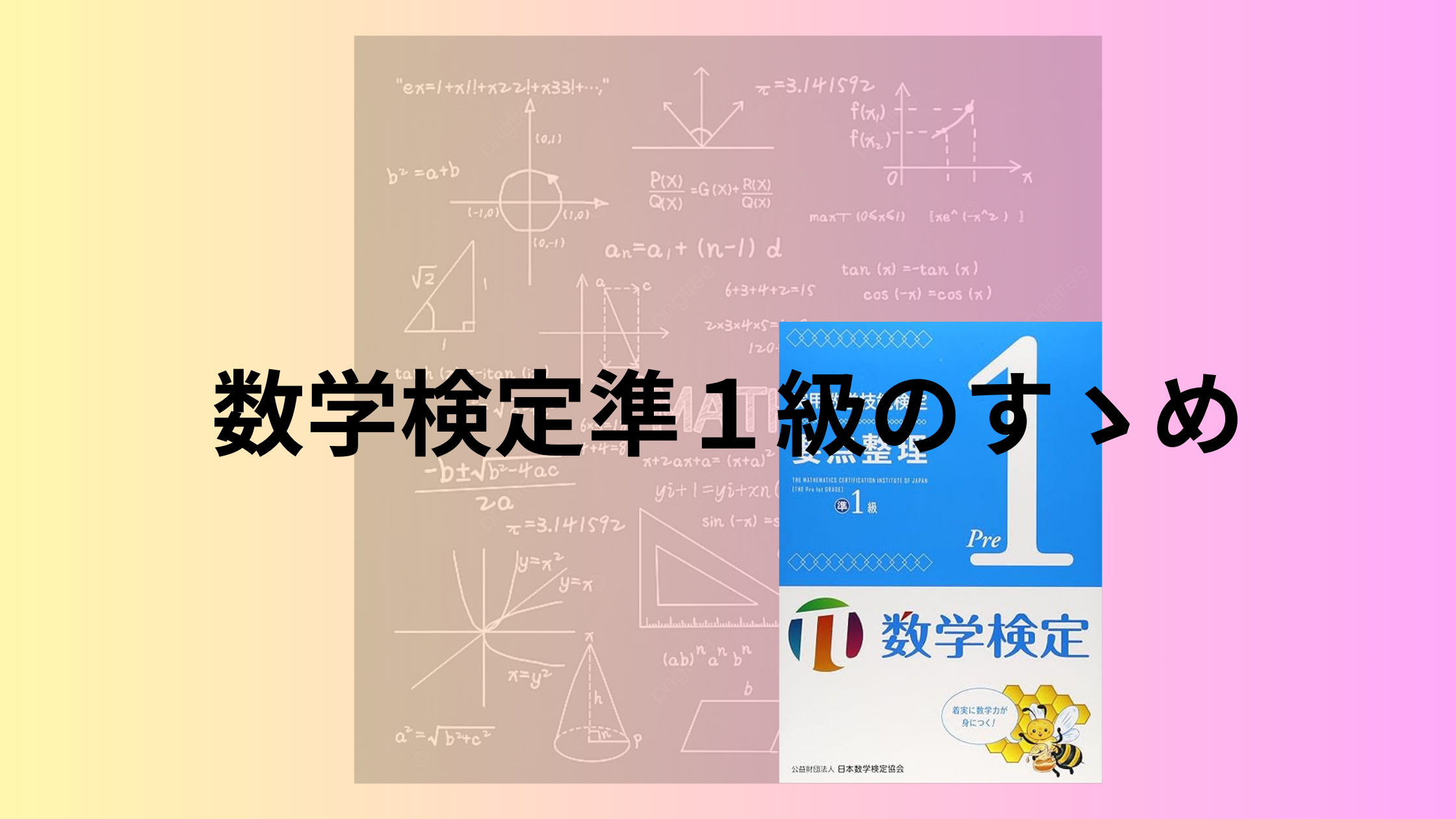
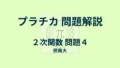
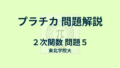
コメント