必要な前提知識
理系数学良問プラチカは、誘導や条件設定の工夫、発想力を必要とする問題が多いので、応用的な問題集を解いてから始める必要はありません。それを解いているからって解けるものでもないです(涙)実際、私は、一通りの学習が済んでいるので、解答を見て解き方でわからないということはあまりありません。ただ、「そんな発想しないでしょ」とはいつも思います(笑)学校配布の問題集などで典型問題を一通り解けるようになったら、いつでも初めていいと思います。
受験生の始める時期
- 現役受験生
→高校2年の冬~3年の春頃。教科書レベルが完成し終えた頃。 - 浪人生
→いつでも。典型問題の解法がある程度わかれば、いつでもいいです。知らないことがあるから解けないというわけでもないです(笑)
受験大学別の始める時期
- 難関大志望(東大・京大・医学部など)
→ 高2冬から早めに始めること推奨。 - 中堅~上位大志望
→高3春~夏に取り組むこと推奨。過去問を解いた方が近道かもしれませんが
理系数学の良問プラチカは何周すればいいか
問題数は一通り学習しておきたい問題135題+やや応用的問題30題=165題です。
一日1問で解いていくと165日、約5ヶ月かかります。全部の問題を何周もすること(回数)を大事にするのではなく、1問1問をどれだけ自分に定着させる(確実な定着)かが大事だと思います。回数は定着にはもちろん必要ですが、あくまでも誘導や発想力を学ぶ、演習強化用教材なので、必ずしも全ての問題を解く必要はないと思います。てか、その方が挫折しないです。
まとめ
理系数学の良問プラチカは、教科書レベルの典型的な解法を知っていればいつでも初めていいです。もし、この問題集をある程度完成させたいなら、高校2年生の冬くらいから少しずつ初めていきましょう。何周もするのではなく、誘導問題の解法や発想力を1問1問確実に獲得していければOKです。ということで自分も毎日1問以上解いて、5ヶ月後にはどうなっているか楽しみです。
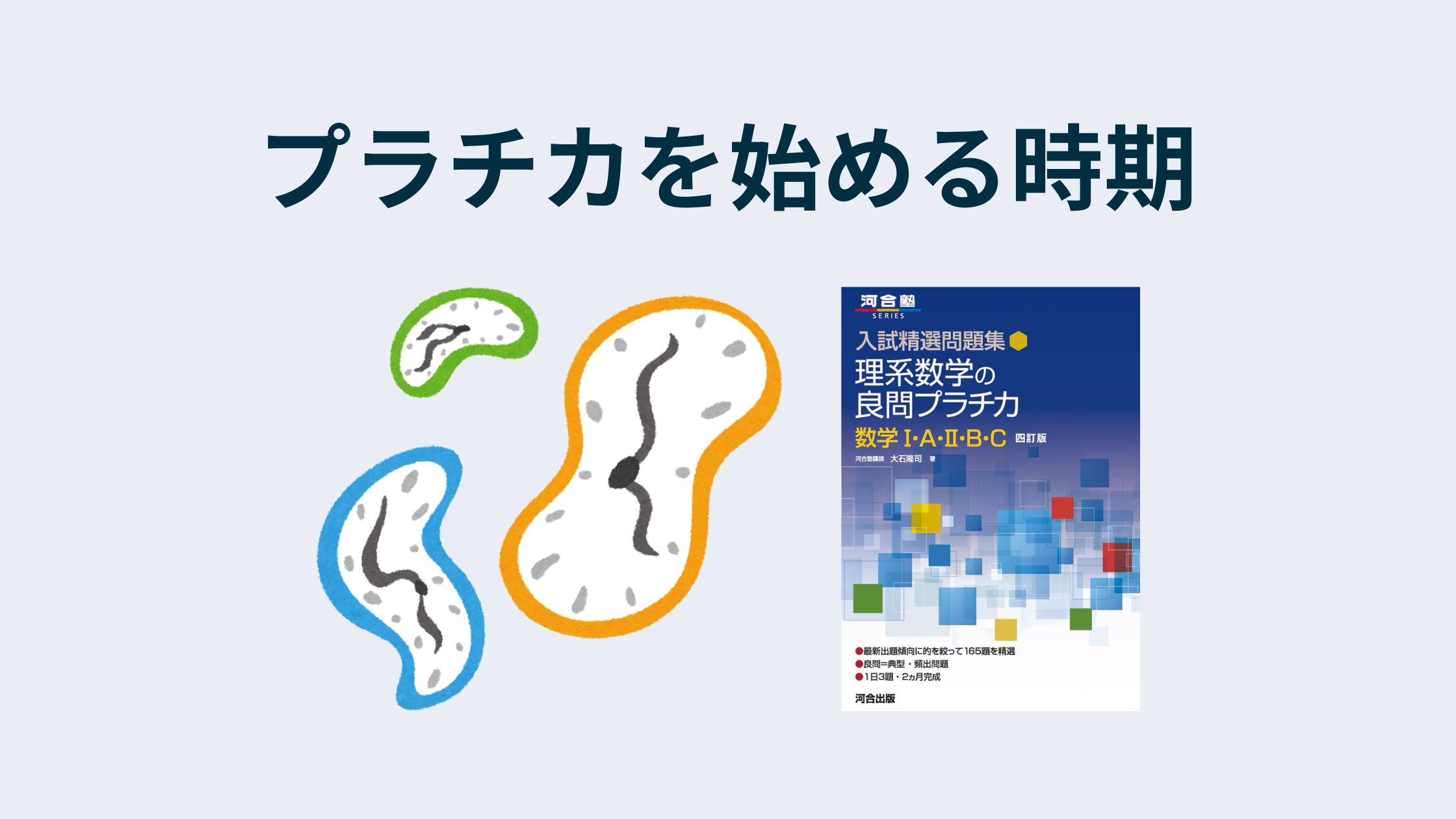
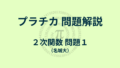
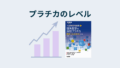
コメント